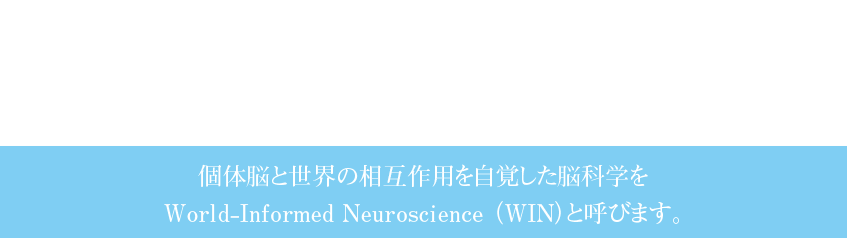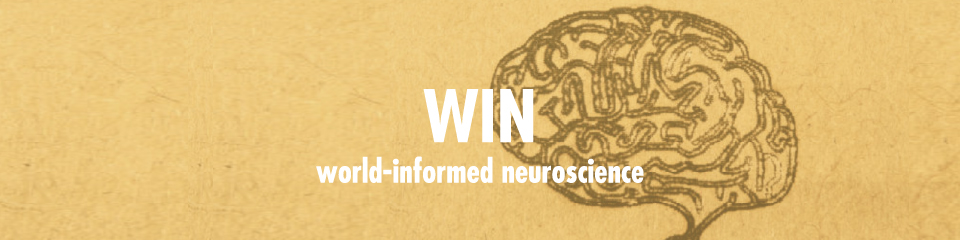個体脳ー世界の相互作用ループ


*** 人間は、予測困難な現実世界(real-world)と切実に向き合う存在である。人の集合や人と人の関係によって成り立つ社会と、自然・人工を含めた環境を総合したものを、ここでは世界(world)と呼ぶが、それは、各個体が物理的に直接作用をもたらす周辺環境(私的世界)のみならず、より広く抽象的な社会構造や文化(公共世界)にまで及ぶ。高度に発展した現代の世界の中で依然として存在するさまざまな生きづらさを理解・解決していくには、人間集団が生み出した世界の特性に対して、個人の特性がどのようにマッチまたはアンマッチするのかという個体と世界特性の相互作用の分析が必要である。一方、これまでの認知科学的なアプローチでは世界特性は所与の一定として問題を個体の認知・脳機能に帰着させてきた。さらに近年ではAIと脳の融合による人間の能力拡張技術を元にした解決策が唱導されるに至っている。しかし、資本主義的考え方、意思を持ち自己決定すること、勤労などの価値や規範に対して、どのように個体特性がマッチまたはアンマッチするのかを無視した脳機能増強や改変は、世界側の変化を要請せず特性が世界とアンマッチしている個体側にのみ適応負荷をかけたり、特性が世界とマッチしている適応者側に偏って利用されれば認知エンハンスメントという倫理課題をもたらしたりする。この背景には本来世界の中で生きる人間を世界から切り出して分析する認知・脳科学と、世界を扱う学術との大きな乖離がある。そこで、これまで実験室で個体を研究してきた認知科学を変革し、現実世界を生きる人々が直面する困難とは何なのか、どう乗り越えていくのか?という問いを、個体と世界の相互作用の観点から明らかにする新しい学術をわたしたちは提案する。これにより自然科学的手法のみによる脳の機能拡張ではない新たな方法で現実世界の問題に取り組む。
*** 人は脳のはたらきにより環境情報を個体に内在化し、個体が環境に働きかける(作用する;action)ことを可能にする。個体と環境は独立に定義できず、個体と個体の関係や個体の集合が社会を作り、それが個体に再帰的に影響を与える相互作用ループが生じることが重要な特徴である。ヒトは報酬獲得と損害忌避のために環境側の法則性を内在化するとともに、より予測が成立しやすいように環境を変化させてきた。人類史においては、個体脳―世界相互作用ループを繰り返して変遷してきた文化要因が生物要因以上に重要な意味を持ってきた。この相互作用ループの解明のため、実験室的環境における少数例の計測研究にとどまっていた脳科学を変革し、偏りの少ない大集団科学(population science)、および大集団コホート参加者を対象とした脳計測研究(大集団脳科学 population neuroscience)を採用する。
*** わたしたちは、個体と世界の相互作用性の解明に向けて大集団科学を採用するという大胆な学術改革を進めてきた。すなわち、2012年に10歳時からスタートし、2年ごとに調査を行ってきたアジア初の大規模思春期コホート(N=3,000)である東京ティーンコホート (Tokyo TEEN Cohort; TTC)を行ってきた。東京という国際的大都市において、思春期の若者がどう世界にコミットしていくのか、という主題を扱うまさに絶好の機会である。大集団科学という普遍性に、時代×世代×地理という歴史上の一回性を掛け合わせた、時・空間大集団脳行動科学という全く新しい学術領域を創出可能である。
*** 社会認知に対応する脳機能を実験室において計測する研究は社会脳科学と呼ばれてきた。しかし現実の世界を考慮せず、脳―世界の相互作用を扱ってこなかった。また、社会心理学や文化心理学等では個体と文化・社会の相互作用について扱ってきたが、個体の生物学的特性やコホート集団の代表性、ヒト独自の思春期発達といった要素を考慮することで、より生態学的妥当性の高い説明を与えるものと考えられる。一方、都市生活や移民状況が脳に与える影響を検討する研究が始まっている。


*** 人間とは何かを問う学術は本来、個体としての人間から世界までを統合的に分析する営みであった。しかし学術史上、人文社会科学と自然科学が分離して以降、自然科学的アプローチによる認知科学や脳科学は、世界との相互作用を考慮せず個体の分析を進めた。一方社会科学は個体と世界の相互作用を前提としてきたが、自然科学的に明らかとなった個体認知機能の脳科学的特性が世界との相互作用に反映されることへの考慮は不十分だった。しかし、現代に生きる困難を単に個体の脳・認知機能の障害や政治・経済制度の不全と捉えるのではなく、個体脳・認知機能と世界の相互作用の中で生じるものとして捉えるためには「法則性」を重視する自然科学と「物語性」の探求を可能にする人文社会科学が連携した新しい目的設定が必要となる。
*** 学術は、自然界の性質を対象とした理系学術と、言葉や対人関係を通じて生み出され、物理的法則に還元し得ない性質を持つ精神や世界を対象とした文系学術に分断されて現在に至る。世界を定数として扱い、世界から分離された脳機能の法則性理解に還元するパラダイムで脳科学は飛躍的な発展を遂げてきた。一方で人文社会諸科学は、人間の人生の物語やその集合としての社会の歴史をナラティヴとして分析し(物語性)、これを自然科学に立脚した脳科学では扱えないとしてきた。
*** わたしたちは、個体脳―世界相互作用ループを理解するために、自然科学に立脚した認知科学・脳科学と人文社会科学とで合意できるモデル化に挑んだ。すなわち個体脳は、世界を法則性と物語性の二次元性で捉えており、またそれぞれを内在化することに対応した脳機構が存在すると仮定した。この仮説は、これまでの、自然科学・生物学=脳の法則性、人文社会科学=世界の物語性という分断をより高い段階で調和するものである。身体や精神に障害がある人の当事者研究から得られた知見から導出されたこの仮説を元に、認知科学と社会学・人類学等の新しい融合研究を生み出す。
*** さらに動物も環境と相互作用して生きていることに立ち返えれば、動物実験においてもこれまでの脳科学を個体脳―世界相互作用ループを扱う新しい基礎科学へと発展させ、法則性/物語性の詳細な神経基盤を因果的に検証することが可能である。これまで予測・予測誤差の認知脳科学は、環境の法則性の内在化を対象としてきた。一方、物語性については、人文社会科学によりナラティヴ分析等で検討されてきた。近年、海馬の場所細胞や記憶エングラム細胞という視点で、マウスの自身の空間的相対位置やエピソード記憶の詳細が検討されてきているが、物語性という観点はまだない。さらには、脳が世界を法則性/物語性の二次元で認識し、一回性の事象から多数回の事象までどのように物語的(エピソード的)に、あるいは法則的(確率的、大数法則的)に回路を切り替えて内在化するのか、という神経科学研究は皆無であり、取り組むべき課題である。